子どもの頃、印象に残った授業ってありますか?変な先生がいたとか、こんな授業が楽しかったとか。
私ミホロボットは、中学生の頃の社会科です。「クイズダービー」と称したクイズ形式の授業。
生徒5〜6人で班をつくり、出題される問題に対して話し合って答える。
正解だと班にポイントが入って、半年間の累計ポイントで優勝決定。優勝者にはハンバーガーがプレゼントされる…というゲーム的な授業で、クラスのヤンキーからオタク、はみ出しものにいたるまで全員が夢中で参加していました。
あのむちゃくちゃヤンキーで他の科目はテスト0点当たり前の彼が、社会科だけ80点を取っている!なんてことが本当に起こっていたあの授業。
変わった授業で面白かったんですよねー、と知り合いの東大阪市立中学校の先生に軽く思い出話をしたところ、「それって河原先生のことですよね?めっちゃお世話になりました!」
そう、河原和之先生。私の中ではクイズダービーの先生。
東大阪の学校界隈だし、知っいてることもあるよねと思っていたら…Wikipediaで発見してしまいました。
河原和之(かわはら かずゆき、1952年 – )は、日本の教育学者、著述家。立命館大学講師、専門は社会科教育論。(Wikipediaより引用)
画面をスクロールすると、経歴や研究などしっかり掲載されています。Wikipediaに載っている=万人が有名と認めるには十分な証拠。ってことは、実はスーパー有名人なのでは…?
河原先生、一体何者?これは詳しく話を聞くしかない!

メールアドレスを知っていたミホロボット、ラブコールを送って取材にこぎつけました。
「確か中1のとき担任やったよな、あ、中3もか?」とおおざっぱに覚えてくださっていた元ミホロボットの担任、河原先生。
現在近畿大学をはじめ、大阪教育大学、立命館大学など8つの大学で講師を務める教育学者です。
代表著書は「主体的・対話的で深い学びを実現する! 100万人が受けたい社会科アクティブ授業モデル」など、教師が授業を実践するための書籍を多く出版。
授業の進め方やネタを考える研究会を主催し、近畿圏の小中学校教師が定期的に集う場も作っています。
今の立ち位置は、平たく言うと「先生の先生」「教材開発者」。めちゃくちゃ学者でした。
そりゃあ東大阪中の先生が知っているし、Wikipediaにも載っているはずです。
明日にでもガイアの夜明けやプロフェッショナルからオファーが来るのでは。
せ、先生、いつの間にそんな偉人になっていたんですかっ!

近畿大学にて、教職の授業を受け持つ河原先生。グループワーク中の一場面。※コロナウイルス感染拡大による大学内立入禁止以前に撮影。
教師界のレジェンドは、いかにしてつくられてきたのか。
「もともと寡黙で、人と話すよりじっと本を読んでる方が好きでしたね。人と話すのが嫌だから陸上部で筋トレばっかりしていたし」と、クイズダービーを軽快な口調で回していた人物とは思えない言葉が。
教師を目指したのは大学3年生の頃。新聞記者になることを考えるも、子どもと関わることで社会の役に立とうと考え、その道を選びます。
しかし目の前に立ちはだかったのは、コミュニケーションという壁。
教師ならば生徒との会話は必須ですが、人と話すことが苦手という致命傷が…。
教師になって1〜 2年は、教壇に立ち教科書を読むだけの授業が続きます。
「生徒からは面白くないと叩かれ、授業を変えていこうと。そこで、教材でコミュニケーションを取ることを考えたんです」。
生徒が面白いと思えるようなネタをつくること。そこから教材の研究・開発が始まりました。

そうそうこれこれ。クイズで正解を出したら得点が正の字で加算されていく。
例えば歴史の授業で「一休さんのお父さんはどんな人でしょう?」というクイズ。
答えは「天皇」ですが、河原先生は立て続けにこう聞きます。「一休さんはお寺に預けられたんですが、なぜ?」
その背景には、南北朝の内乱が。父が北朝側、母が南朝側で対立関係にあったためお寺に預けられた、というストーリーが出てきます。じゃあ、そこから南北朝時代とはどういう時代だったのか…と、芋づる式でテーマが広がり、気づけば体に物語が染み込んでいく。
ほかにも、チョコレート菓子「コアラのマーチ」から見た地球温暖化や、東京オリンピックを通した国際情勢の見方など、身近でないものに親近感をもたせるのが河原流。
こうしたネタづくりが生徒に耳を傾けさせ、記憶に残る授業になっていくのです。
授業を授業と思わないような面白さや意外さがあれば、生徒は飛びついてくる。常識では考えられない教材を開発することで、今のスタイルを確立してきました。
数ある教科から社会科を選択した理由は、工夫ができて楽しいから。
「暗記すれば良い教科だと思いがちですが、社会科は『考える教科』なんです。背景や文脈から、ストーリーを考えられる」。
教師生活37年、東大阪市内の公立中学校や東大阪市教育センターで経験を積み、一時病床に伏したものの復帰。
次は教師や教師になろうとしている大学生に教える立場となり、教育界のレジェンドに。

「クラスをまとめる」とはどういうことか、自身の経験と実践を学生に話す。
「教師として子どもたちに望むのは、世界に興味をもって、突っ走ること。これだけ世界が近くなってきているのだから、異質な人とのコミュニケーションをとっていかないといけない。それが多文化共生ってことなんじゃない?」
河原先生は、教育の行く先を見据えます。
最後にお邪魔したのは、8月16日に54回目が開催された「ネタ研」。近畿圏内の小中学校教師が集まって授業のモデルケース発表や意見交換を行う、授業のネタ研究会です。
「自分、ラグビーのこと取材したりイベントしたりしてるんやろ?よかったらどんなことしてるか発表して」とふられたミホロボットが、なぜか登壇することに。

ラグビーワールドカップに向けた週ひがの取り組み発表と、パネルディスカッションに参加しました。
何でも貪欲に取り入れ授業のネタに昇華していく河原先生は、やっぱり教育界の生きるレジェンドでした。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。























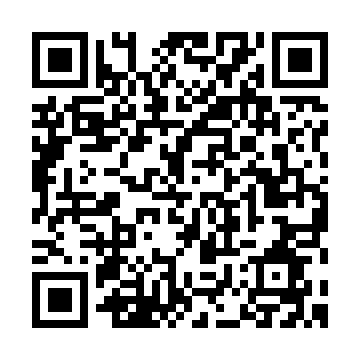
 (2024.08.28)
(2024.08.28) (2024.08.24)
(2024.08.24) (2024.07.31)
(2024.07.31) (2024.08.23)
(2024.08.23) (2023.08.15)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。