他市から東大阪市に引っ越してきた人が、高確率で読めない難読地名「八戸ノ里」。ちなみに「やえのさと」と読みます。決して「はちのへの・・・」とかではありません。
そんな、ちょっと読みづらい、ローカル色バリバリの地名も「YAENOSATO」と書かれると、ちょっと違って見えちゃいます。
今回はただいま近鉄八戸ノ里駅の南に計画中の、YAENOSATO PALET SCAPE(やえのさとぱれっとすけーぷ)という取り組みを取材してきました。

このパース、やばくない?
こんなパースまで作る、気合いの入った取り組みを主導するのは、近畿大学建築学部垣田博之准教授。八戸ノ里駅の南に、搬送用の木製パレットを材料とした、街の人々が集まるスペースをと現在奮闘中です。

近畿大学33号館に展示されていたパレット。これ見たことある!
「パレットは荷重に強く頑丈なのに、使い終わると捨てられます。これを利用して、地域に賑わいをと考えて計画しました。」
プロジェクトには、八戸ノ里商店街もバックアップ。空き店舗を作業場として提供し、垣田先生や学生さんが作業しやすい環境を整備しています。
しかし、どうも何ができるのかよくわからない。記者のピンと来ない表情を見て、
「今、大学にイメージを展示しているんで見に来ませんか?」と垣田先生。
それじゃ、ということで近畿大学33号館1階に、押しかけると、そこには。

こうやって見ると、八戸ノ里のイメージが変わる?
うわ!八戸ノ里が展示されている!
「まずは、何ができるかを、周辺の駅やビル、景観も含めて模型で再現しました。そこにPALET SCAPEがあると、ちょっとしたもんでしょう」

これができるのか!と模型にときめく記者。
なるほど、八戸ノ里って確かにこんなだったよなと思わせるジオラマに、出現予定のPALET SCAPEが。こう見ると、何かが起こりそうな気がします。ふらっと立ち寄る人もいれば、休憩に座る人もいる。学校帰りに友達とおしゃべりする学生さんもいるでしょう。もしかしたら、コーヒーをテイクアウトして、、、とイメージが膨らみます。

こちらは道路側から。開放感が上昇するのは間違いなさそう。
「ここから見ると、八戸ノ里って違って見えるでしょ」「駅からこれがこんな風に見えれば、、、」など垣田先生は頭のなかではすでに「YAENOSATO PALET SCAPE」は完成形。地域のデザインって、駅前再開発のような大規模な工事以外でも、できることがあるんですね。先生は八戸ノ里をどうする気なんだろう。

先進事例を説明してくれる垣田先生。
実はこのプロジェクト、2019年八戸ノ里駅北側に完成予定の新市民会館のオープンに向け、周辺のにぎわいを創出しようという取り組みの一環。世界中の事例を研究し、八戸ノ里で何ができるのか、練りに練ってスタートしたんだそう。想像以上に大きな流れの中にあるのです。
また、社会実験という側面もあります。東大阪市はいわゆる「まちづくり」に役立つ研究に対し、助成金を用意。このプロジェクトもそれを活用し、期間限定で設置されるのです。
さらにジオラマの隣には、八戸ノ里のなんでもない風景写真とパレットの展示も。こんなに八戸ノ里をデザイン的に切り取った空間は、おそらく史上初でしょう。

記者もパレットに座りながら、八戸ノ里を堪能。
YAENOSATO PALET SCAPEの完成は3月上旬を予定。なのはなが咲き、人が行き交うなかで、どんな役割を果たしていくのか。今から完成が待ち遠しいいです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。























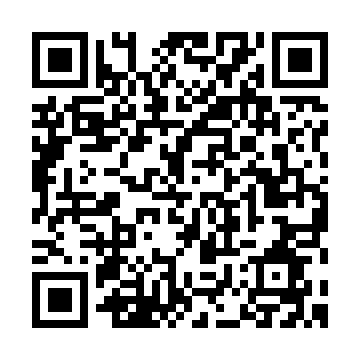
 (2024.08.28)
(2024.08.28) (2024.08.24)
(2024.08.24) (2024.07.31)
(2024.07.31) (2024.08.23)
(2024.08.23) (2023.08.15)
(2023.08.15)
駐輪場横の茂みに黒猫が3匹住んでいます
餌をあげて世話をしている人が数人居ます
なるべく彼らを脅かさないように…願います…
コメントありがとうございます。
猫たちと共存できたらいいですね。