- Home
- 新型コロナウィルス感染症, 暮らし
- 新型コロナ第6波を迎え、ITを駆使して危機を乗り越える サンコーインダストリーのクリティカルな取り組み
新型コロナ第6波を迎え、ITを駆使して危機を乗り越える サンコーインダストリーのクリティカルな取り組み
- 2022/2/17
- 新型コロナウィルス感染症, 暮らし
- コメントを書く
こんにちは。新型コロナウィルスが社会を変えてしまってもう2年が経ちます。
かくいう週刊ひがしおおさかも、巣ごもりや地元回帰で地域の皆さんに注目していただき閲覧数が爆上がり。日々の陽性者情報を発信したり、なんとかお役に立ちたいと思っています。
とはいえ今年に入ってからのオミクロン株の流行による第6波には、今までにない変化を感じたりも。
さまざまな情報が行き交って行動までに時間もかかったり。
そんななか、独自の新型コロナ対策を実行するねじの専門商社サンコーインダストリー株式会社(以下サンコーさん)を紹介します。週刊ひがしおおさかの読者の皆さんにはすっかりお馴染み、中央環状線沿いにでっかい物流センターを持つ業界最大手。ラグビーボール型のオブジェを東大阪市花園ラグビー場に寄贈したりと、なにかとお世話になってます。

いっぱい物流センターがあるんだけど、なかでもこの「長田センター」にはトライくんが。
感染の拡大が懸念された2020年の春、「濃厚接触者を出さない」ことに対策の重点をおいてきたサンコーさん。
・企業活動の継続には働く人たちを濃厚接触者にしない対策が重要
・濃厚接触者を減らすことが全体の陽性者を減らすことにもなる
と、いち早く社内で共有されます。
同時に独自のガイドラインを設け、不安があればすぐに総務課が相談に乗る体制を作りました。
実は週刊ひがしおおさかも、グループ会社(株主さんでもあります)のよしみで何度か相談にのっていただいたことも。
他にも、独自で数理モデル(とても複雑な数式)を使った新型コロナ新規陽性者の予測も実施。社内に掲示するとともに、週刊ひがしおおさかで配信しているコロナ予想もそのデータをお借りしています。
しかし今回の第6波は、早さも波の大きさも今までとは比べものになりません。今までの対策が十分でないことも。そんな状況でサンコーさんはどう動いてるのでしょう。

サンコーインダストリー株式会社の奥山社長。新型コロナ対策の陣頭指揮を取る。
「早期発見と早期隔離が特に重要なことがわかってきました。」
と話すのは、サンコーインダストリー株式会社代表取締役社長の奥山さん。サンコーさんでは、2年前から蓄積してきた社内での相談をすべてデータベース化。
相談があればすぐ入力し、担当する社員さんが履歴をたどれるようにしています。
「多くの社員の皆さんから『どうしたらいい?』という問い合わせが相次ぎます。もちろんご自身が感染したという事例から、子どもさんが学級閉鎖になったという事例も。総務と社長と4人体制で相談にはすべて応えています」と話すのは、総務部部長の佐藤さん。

奥山社長が自ら開発した、管理アプリ。写真提供:サンコーインダストリー
・致死率が低い
・症状は発熱が主
ということ。さらに
「うちの経験では、無症状感染って人がほぼいないんです。よって症状に気が付かないケースが無症状だと仮定すると、マメな体温管理で早期発見と早期隔離が可能になると考えています。」
と奥山社長。
「経験」とは、2年間で受けた相談約120件。それがすべてデータベースになっているので、傾向が見えるのだと言います。

相談を受けていた佐藤部長。新型コロナ前は編集長とも酒席をともにしました。
現在サンコーさんでは、部署ごとに毎日3回の検温を実施しています。朝礼時、昼休憩後、退勤前などタイミングを決めて全員が検温。なかには自主的にデータベース化して、乖離した値を割り出す社員さんもいるそう。
いや、待って。どうしてそんなにみんな協力的なの?自主的なの?
「今目の前のめんどくさいことをしないと、長期的な成果は得られないって意識は常に話しています。TQC活動にも力を入れているのもそれですね。」と奥山社長は言います。
TQC活動とは
Total Quality Controlのこと。仕事の課題や目標をテーマに業務の品質や効率を向上させる活動で、経営体質の充実と強化を図る手法です。
※出典:サンコーインダストリー公式サイト
「でも、最初はやっぱり抵抗ある人もいましたよ。僕みたいなおっちゃんが、年下の女子社員の体温を測ったりするわけですから。でも、普段からキャンペーンをしてノリを大切にして、どうせなら楽しんでいこうって。」と話す中村さん。実は、つい先日新型コロナから復帰したところだったんだとか。

新型コロナ前は一緒にガンプラを作ってくれた中村さん。笑顔が眩しい。
佐藤「体温を計ろうってなって、会社で買って部署ごとに配布したんです。そのテストをしていたら、中村の体温が高いぞと。」
中村「朝は36.3度やったんですよ。それが、昼に測ったら37.5度。他の体温計で測り直したら38度台で…。」
その後中村さんは、会社からPCR検査を受け陽性に。自宅での待機になりました。
サンコーさんでは、社内での陽性になった人にはまず以下のような案内をしています。

「2年間の経験で、家庭内感染に対して効果があったんじゃないかって事例を並べています。『隔離ってそんなん家の中で無理やん!』って声もよく聞くんですけど、経験上こういうことでもリスクは減る。まずやってみるってのが大事やと思います」
と話す奥山社長。とともに「もはや陽性者を出さないことが重要な論点ではない。」とも。
一見振り切った考えにも見えます。しかし、拡大をさせないという視点に立つと
「自分たちが感染しない」
ことと同じくらい
「他の人になるべくうつさない」
は重要なこと。
致死率が低く、主な症状が発熱だと判明すれば
「他の人にうつさないこと」
に比重が置かれるのは非常に論理的です。
そのためにはコロナがどうこう以前に、マメに体温を測って体調が悪ければ休んで治療に専念する。それがもっとも効果的で、社会全体の拡大を妨げることにもつながる。
そこへサンコーさんが得意とするITの力で、情報を共有し判断のタイムラグを減らす。週刊ひがしおおさかは、「アプリで情報共有しスピード化」って言葉をここまでベタベタにやってる例を知りません。
当たり前ですが従業員4人の週刊ひがしおおさかは3桁後半のスタッフさんがいるサンコーさんとは、企業規模は違います。だからって↑の取り組みが参考にならないなんてありません。
スマホアプリを開発できなくても、スマホで情報を共有したりルールを明確にすることは可能。毎日数回体温チェックをして、共有したり履歴を取ったり体調管理はできちゃうはず。
取材の最後に奥山社長がいいました。
「みんな誰かに判断を委ねちゃうんですよ。でも結局は自衛するしかないでしょ。だから事例からノウハウをためてやれることをちゃんとフィードバックする。みんなに『守ってくれるんだ』って思ってもらわんとね」

「コロナって言っても勤怠管理してるってことですからね。」と奥山社長。
自分たちにあった対策やコロナとの付き合い方を常に模索することは難しくない。
2年間でみんないろいろ経験した。情報も増えてきた。
そろそろ自分たちで考えて、しっかり学びを活かしていく時期になったのかもしれません。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























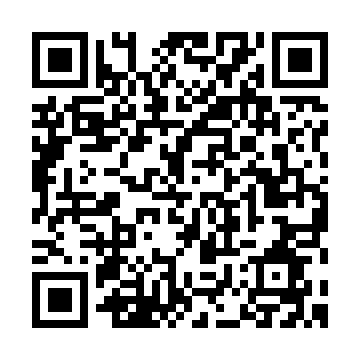
 (2024.08.28)
(2024.08.28) (2024.08.24)
(2024.08.24) (2024.07.31)
(2024.07.31) (2024.08.23)
(2024.08.23) (2023.08.15)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。