コロナで停止した東海大、帝京大のスタミナ削り攻撃に耐えるも惜敗 コロナ下におけるスポーツの活動から何が得られるのか
新型コロナウィルスが猛威を振るうなか、大学選手権を開催し1月からはトップリーグ・トップチャレンジリーグが開幕する日本ラグビー界。
当たり前のようにチームやスタッフから感染者が出るなか、一旦立ち止まりつつも活動を続けています。
12月19日(土)に花園ラグビー場で行われた大学選手権準々決勝第1試合は、リーグ戦最終盤でコロナにより試合を棄権した東海大学と、夏に活動を再開してからは比較的順調に進んできた帝京大学が対戦しました。
東海大学は果たしてどこまで戻してくるのか。活動を停止した影響はどの程度なのか。

帝京大の突破を3人がかりで止める東海大。
キックオフから帝京大学はFW戦を仕掛けてきます。練習期間が中断して真っ先に影響を受けるのは、持久力。フィジカルに勝るチームが削るように体を当てます。
リードしながらゲームをコントロールしたい東海大学は前半5分にPGを決めて3-0とします。帝京大学は強みのスクラムでゲームを作ります。
前半33分に敵陣左奥でペナルティを得た帝京大学は、スクラムを選択して押し続けると、東海大学はペナルティを連発。トライを反則で防いだとして、ペナルティトライを帝京大が得ます。やっぱり、東海大はフィジカルで負けこのまま下げられていくのか。

モールで押し込む帝京大。FW戦では、やはり東海大を上回った。
しかし、さすが関東リーグ戦の覇者、東海大は違う。巧みに当たりをずらしながら、エリアを取って接点での負けを致命傷にしません。また、帝京大のラインアウトをたびたび奪ってピンチを脱出。前半は3−7で折り返します。
後半息切れすれば、一気にワンサイドゲームになってしまいそうな展開。14分に帝京大14木村朋也がトライを奪い、3−14。

後半は、木村の右サイド突破が目立った。
もう無理、突き放される。
9連覇時代は、前半に堪える相手の体力を当たりで削り、後半ボコボコにしていた帝京大。しかし東海大はここでも踏ん張ります。それどころか、後半26分にトライを返し8-14まで追い上げます。あと1トライ1ゴールで逆転。

モールから、東海大17土一海人が押し込んでトライ。逆転なるか?!
ただ、あと1本が奪えなかった。
試合後、東海大学の木村季由監督は「コロナの影響があったからといって、その後特別な練習をしたことはない」と話します。

記者会見は、オンライン会議アプリ「zoom」で行われました。
感染者が判明し、活動を一時停止してもやることは、できることは変わらない。なら、ラグビーはコロナに対してただなされるがままなのか。
東海大学が練習を再開したのは12月12日頃とのことで、11月29日にクラスターが確認されてから2週間何も出来なかったことになる。
感染自体は不確定要素が多く、タイミングに寄ることも多い。なら
・感染者が出ても活動を停止しないためにはどんな準備ができるのか
・停止せざるをえないとしても、停止期間をいかに短くするか
が課題になってくるでしょう。
活動停止しないためにはクラスター化させないことが必要で、停止させないためにはまず濃厚接触者を減らさなければなりません。
そして感染症対策という、新たな要素がスポーツに加わることは、必ずしもスポーツの魅力を減衰させるわけではありません。
スポーツとは、社会の縮図。だから人々に活気と潤いを与える。
多くの知見を、立場の垣根を越え素早く共有しトライ&エラーを繰り返す。社会とスポーツが、新しいステージに入ろうとしているのでしょう。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。























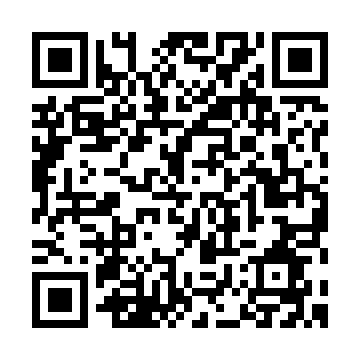
 (2024.08.28)
(2024.08.28) (2024.08.24)
(2024.08.24) (2024.07.31)
(2024.07.31) (2024.08.23)
(2024.08.23) (2023.08.15)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。