花園ラグビー場で東大阪市新規採用職員の辞令交付式を実施 二ノ丸友幸さんによる研修も
新元号が「令和」に決まった4月1日(月)。世間では入社式が多く執り行われたことでしょう。
そんな中、東大阪市でも東大阪市役所新規採用職員の辞令交付…つまり入社式が行われました。
今年はラグビーワールドカップイヤーということで、東大阪市花園ラグビー場で初めて実施されました。
参加したのは平成最後の、そして令和元年の東大阪市に新規採用が決まった79名。

初めに、野田義和東大阪市長から一人ひとりに辞令が渡されます。

辞令交付が終わると、新規採用職員による宣誓。

「全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を全うすることを誓います」と、公務員らしく堅実な宣誓をしました。
続いて、野田市長によるあいさつ。

「今年はここ花園の地でラグビーワールドカップが行われ、東大阪市は世界が注目する都市です。市全体の奉仕者ということを自覚して、職務を全うしてください」と、激励しました。
辞令交付式と同時に、近畿大学出身でパラ水泳競技で活躍する一ノ瀬メイ選手のスポーツみらいアンバサダー就任式も行われました。
東大阪の魅力発信や都市ブランドの向上を図るため、市にゆかりがあるアスリートをアンバサダーに任命している東大阪市。
一ノ瀬選手は、4月から新社会人として近畿大学職員になるため、同じ「1年生」として招かれました。

一ノ瀬選手は「スポーツみらいアンバサダーとして、次の世代にもスポーツの魅力を伝えていきたいです。私も新社会人になって1年め。共に東大阪を盛り上げていきましょう」と、意気込みました。

野田市長から特大名刺のプレゼントも。

さらに、サプライズゲストとして同じくアンバサダーの上山友裕選手が登場。社会人の先輩として、メッセージを送りました。
続いて、「ラグビーワールドカップ2019™ルーム」に移動して、野田市長の講話。

「返事、あいさつ、声、ダッシュを意識して仕事に取り組んでほしい。特にあいさつができない人は社会人としても失格。市役所内外であっても、あいさつは必ずするように」と、社会人としての心構えを伝えました。
講話の後は、再びラグビー場に戻り、集合写真。

週ひがも写真を撮らせてもらいました。
式は終わりましたが、研修は続きます。
4月1日のビッグニュースといえば…。そう、新元号の発表日。

新元号発表の瞬間にトライくんも駆けつけました。しっかりカメラ目線の野田市長。
なんと、花園ラグビー場のビジョンに映像が映し出されたのです。
その場にいる全員で、発表の瞬間を見守ります。

こんな大きなビジョンで見ることができるなんて。東大阪で、いや日本で一番大きく「令和」を見たかもしれない。
新規採用となった峯千春さんは、「今までは平成で若い世代と言われてきました。これからは令和生まれの後輩ができ、自分たちが責任を果たしていかないといけないと思います」と、意気込みました。

ここで午前の部は終了。午後からは「ラグビーワールドカップ2019ルーム」に移動し、元ラグビー選手で東大阪出身の二ノ丸友幸さんによる研修が行われます。

啓光学園高校(現常翔啓光学園)出身の二ノ丸さん。
二ノ丸さんによる研修は昨年12月にも行われ、今回で2度め。「社会で活躍する人材とは〜Great Business Personをめざして〜」と題し、「Q:研修とは何のためにするのか」「Q:学生と社会人の違いは」「Q:社会で求められる人材とは」など、質問を投げかけグループで考えさせて答えを導き出させます。

二ノ丸さんは、「私自身の経験を踏まえて話しているので、身近に感じてもらいたい。明日から実践できることを伝えているので、すぐに活かしてほしい」と話しました。

せっかくなので、ラグビー場をバックに撮らせてもらいました。
1日研修を取材させてもらったホッケー梶間ですが、なんと新規採用職員の中に大学時代の同級生・山本くんを見つけちゃいました。しかも、出身地も同じ山口県。
せっかくなので、新社会人になった意気込みなどを聞いてきました。

職場は、東大阪市上下水道局の山本くん。
ーどうして東大阪市を選んだのでしょうか。
山本 大学で4年間大阪に住んでみて、人の暖かさが好きだなと感じました。土木の勉強をしたことを活かしたくて、水道局員になりました。他市では市役所職員と水道局員が一括りの土木採用で、どちらに勤務するかわからないのですが、東大阪市は区別されています。確実に水道局に勤務できるので、魅力を感じました。
ー職員になっての意気込みを教えてください。
山本 新入社員だからこそのフレッシュさを活かして仕事をしていきたいと思います。あいさつとスピードも意識したいです。仕事の早さだけではなく、書類をもらいに行くときなんかも素早く行動していきます!

新規採用職員のみなさん、令和時代の東大阪をよろしくお願いします!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。























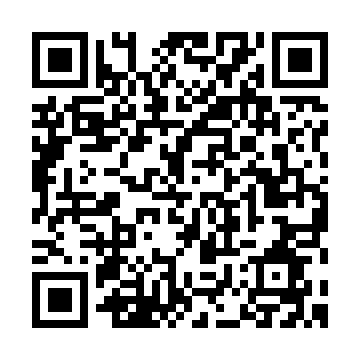
 (2024.08.28)
(2024.08.28) (2024.08.24)
(2024.08.24) (2024.07.31)
(2024.07.31) (2024.08.23)
(2024.08.23) (2023.08.15)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。